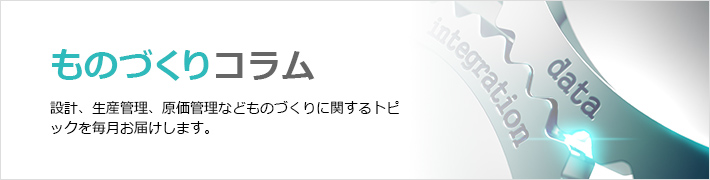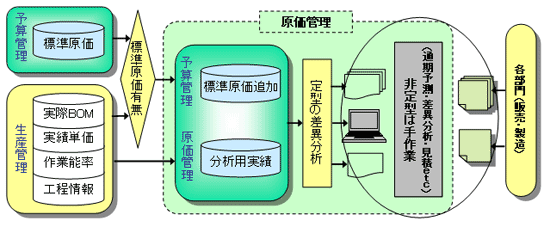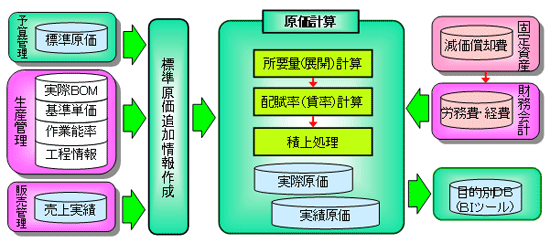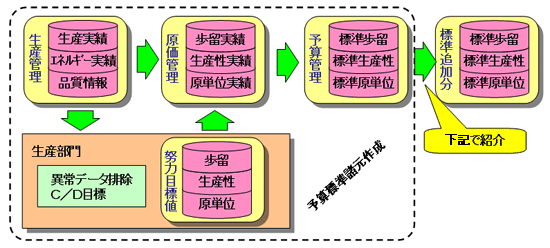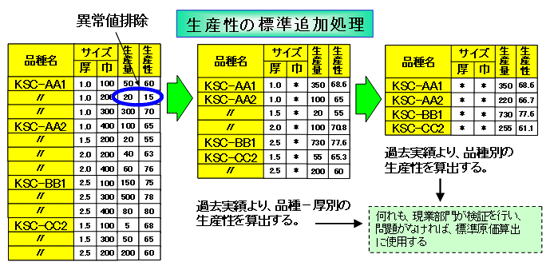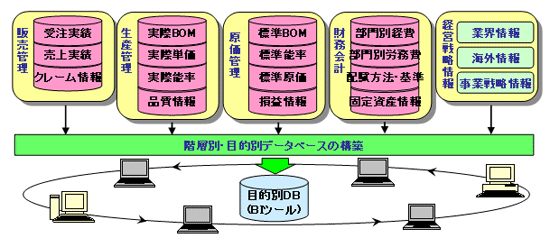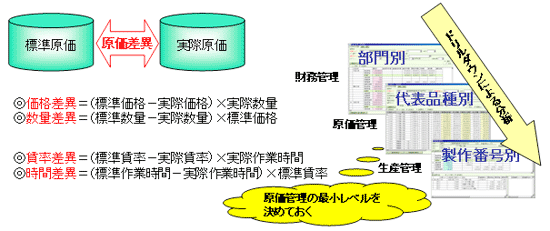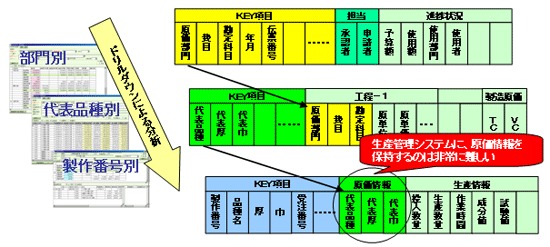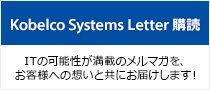2009年06月01日
原価管理よもやま話③
製造業における『月次原価管理システム構築』のポイント
第1回目では、企業における管理サイクル(P→D→C→A)および予算管理(予算編成)システムの課題〜解決策、更には予算編成システムの前提条件を述べてきました。
第2回目では、予算編成スケジュールの短縮について、システム面からの変革ポイントを説明してまいりました。
今回の第3回目は、月次決算における原価管理システムについて、システム面の変革ポイントを説明してまいります。
| 1. | 原価管理システムの現状 | |
| 1. |
月次原価管理システムの現状認識
図-1 原価管理システムの現状
上図でもお分かりになると思いますが、生産実績の計上に合わせて、標準原価の有無をチェックし、無ければ改めて追加作成する処理を行なっています。 |
|
| 2. | 新原価管理システムの構築(案) | |
| 1. |
実際原価計算、原価差額分析システム構築のポイント
図-2をご覧下さい。現行システムの手作業部分がシステム化され、関連するシステムとインターフェースを介して発生原価を集計〜配賦計算し、実際・実績原価計算が可能なシステムへと変革し、更には、バッチ処理が極小化されたシステムになっています。
図-2 月次原価管理システム |
|
| 2. |
予算データ・実績データの有効活用
図-3は、標準原価の追加で必要となる、原価諸元(部品表、歩留、生産性、原単位など)を予算編成時の予算データおよび月次実績のデータより自動作成する考え方を示しています。
図-3 予算データ・実績データの有効活用
生産管理の実績データを標準原価用に加工する仕組みを構築しますが、主管部門である現業部門の承認が必要になります。 図-4は、標準原価追加用生産性を生産管理の実績システムより、異常値を排除したり、実績のない標準生産性を作成する考え方を記述したものです。
図-4 実績データ有効活用のポイント1 図-5は、第2回目の説明でも記していますが、標準原価算出用歩留を生産管理実績システムより、異常値を排除したり、実績のない標準歩留を作成する考え方を記述したものです。
図-5 実績データ有効活用のポイント2 |
|
| 3. |
階層別・目的別データ・ベース構築のポイント
現行の原価管理システムはシステム化がされていても、定型帳票や定型画面からの画一的な情報提供でしかなく、新しい情報を入手しようとすると、その都度システム部門に依頼をしなければならない仕組みになっています。 図-6に、そのイメージ図を示します。
図-6 階層別・目的別データ・ベースの構築 |
|
| 4. |
原価差額分析ドリルダウンのポイント
原価管理システムの最後の変革は、EUCの実現と合わせてドリルダウンが可能な仕組みへと変革する事にあります。 そのイメージは、図-7と図-8に示します。
図-7 原価差分分析の範囲1
図-8 原価差分分析の範囲2 前述の各施策を構築することにより、月次原価管理システムの変革が行なわれ、業務改革と合わせて効果的な原価管理業務が推進できます。 次回はコストダウンに的を絞ったシステム構築のポイントを説明したします。ご期待下さい。 |
|
2009年6月
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読