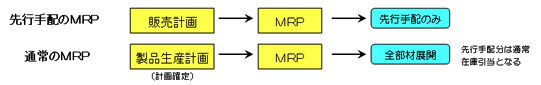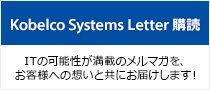2009年09月01日
生産管理システム構築の10ポイント ②
製品の多様化への対応 部品表の工夫
機械、電機、電子機器等の組立系企業では部品表に基づいて原材料・部品の調達手配、製造指示等が行われており、部品表管理は重要な機能となっております。業務を効率的に行う上での部品表の管理、利用についていくつかの考慮点をご紹介いたします。
| 1. | 部品表の構成における工夫 |
| 1.部品表の構成の条件選択 | |
|
製品機種は同一であるが電圧、型式、オプション等により部品表の一部が異なる場合にそれぞれを組み合わせた部品表の作成が必要となります。この方法で品名、部品表を設定すると数多くの品名、部品表の設定が必要となります。この対応策として機能・仕様などにより条件づけした部品表ができれば品名、部品表の設定量を大幅に減少させ、部品表管理を容易に行なうことができます。
|
|
|
上記は機種コードが製品の共通品名を表現し、条件1、2に型式等のコードを設定したものです。条件が2つ程度であれば、問題ありませんが、条件が増加すると運用が困難になります。
|
|
|
この方法は品名と機能条件を分割したものであり、複数の機能条件を設定することができます。 各機能条件に名称を設定して、品名に対して該当する機能条件に値を設定して製品を定義します。 最近は顧客ニーズの多様化により、製品のバリエーションが増大・複雑化する傾向にあり、システムの対応としては、品名と機能条件を分離する手法が一般的になってきています。 |
|
| 2.構成条件選択と組合せ可否の考慮 | |
|
|
|
|
上記例は各条件全てに対して構成可能ではないため、品名−各条件の相関により製造可否を判断する組合せ可能マスターが必要となります。この組合せ可否の判断は受注時にチェックすることが必要です。 ここまでご紹介したこの部品表の工夫の更なる活用として、製品コンフィグレータへの展開があります。 「製品コンフィグレータ」とは、製品の機能・仕様から製品品番を特定する仕組みです。皆様がよくご覧になっている例を挙げますと、インターネット上でPCのCPU、メモリ、ハードディスクなど仕様を項目ごとに(他との相関から選択可能なもののみ)表示される選択肢を一つ一つ設定していくと、最後に品番と標準価格が表示されるあの機能です。 このように部品表を工夫することで、営業部門の業務効率化ツールとして発展させることが出来ます。 |
|
| 2. | 先行手配を容易するための部品表 |
|
|
|
|
部品表はシステムの基幹情報として多くの業務処理で参照されます。部品表のあり方を工夫することで業務の効率化ができます。貴社の部品表の工夫にチャレンジしてはいかがですか? |
2009年9月
最新の記事
年別
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読















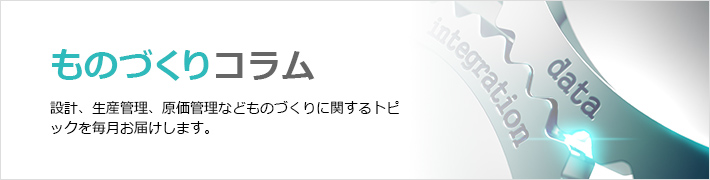
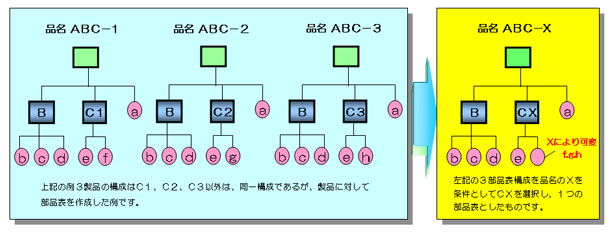
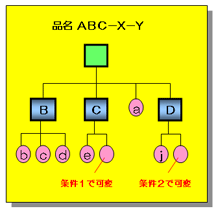 右図の条件構成表の例は品名の一部を構成条件としており、この場合は下記のように品名を体系化させる必要があります。
右図の条件構成表の例は品名の一部を構成条件としており、この場合は下記のように品名を体系化させる必要があります。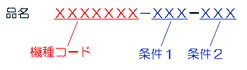
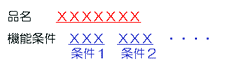
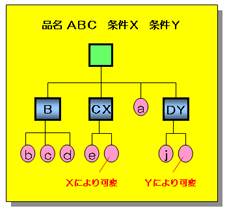 右図は品名ABCに対して条件が2つある例です。
右図は品名ABCに対して条件が2つある例です。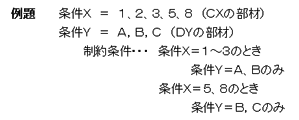
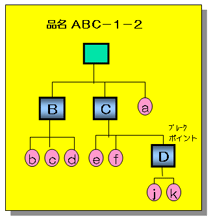 製品の製造において短納期対応するため、先行手配を行なう場合があります。先行手配は製品の場合と部材の場合があり、ここでは部材の先行手配について説明します。
製品の製造において短納期対応するため、先行手配を行なう場合があります。先行手配は製品の場合と部材の場合があり、ここでは部材の先行手配について説明します。