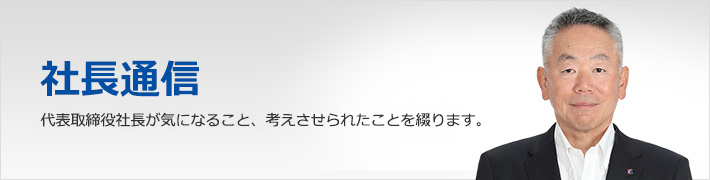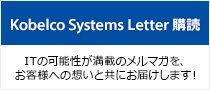2025年09月01日
野球界で加速するDH(指名打者)制の採用
~スペシャリストの時代を考える~
 日本高野連は8月1日、2026年の公式戦からDH(指名打者)制を採用すると発表しました。この制度は来春のセンバツ大会から実施されます。これは部員数が減少する中、新たな活躍機会の創出や投手の負担軽減が目的で、現場の監督からも「守備は苦手だけど打撃が得意な選手など、いろいろなタイプの選手が試合に出る機会が広がる」と歓迎の声が多く上がっています。
日本高野連は8月1日、2026年の公式戦からDH(指名打者)制を採用すると発表しました。この制度は来春のセンバツ大会から実施されます。これは部員数が減少する中、新たな活躍機会の創出や投手の負担軽減が目的で、現場の監督からも「守備は苦手だけど打撃が得意な選手など、いろいろなタイプの選手が試合に出る機会が広がる」と歓迎の声が多く上がっています。
すると、これに続いて同4日には、プロ野球のセントラル・リーグがついに2027年シーズンからの導入を発表しました。これでメジャーリーグ(MLB)や主要な世界大会を含め、ほぼ全世界の野球界がDH制で試合をすることになりました。
DH制は1972年に投高打低の傾向が強く観客動員にも苦しんでいたMLBのアメリカン・リーグが採用し人気を回復、日本では人気低迷にあえいでいたパシフィック・リーグがその成功を参考に1975年から採用しました。メリットは打撃に秀でた選手を起用できるだけでなく、守備の負担が軽減されればベテラン打者の寿命も延びます。対する投手は攻撃で代打を送られる可能性がなくなるため先発の投球回数が増える可能性が高く、投球に集中できるためレベルアップにもつながります。実際にDH制の導入によって、打つこと、投げることなど「一芸に秀でた」魅力的な選手が数多く輩出されました。
ビジネスの世界でも「一芸に秀でた」スペシャリストの人材価値が上がってきています。例えば国内では、少子高齢化によって労働人口が減少している中、生産性を高めるにはAIやIT技術など新しいテクノロジーの活用が必要不可欠であり、その専門知識を持つ人材の需要が高まっています。
雇用環境の変化もスペシャリストの価値を後押ししています。長年、日本企業の特徴であった終身雇用や年功序列などの古い人事制度の見直しが進んでおり、今より良い労働条件を求めて転職することも当たり前になっています。特定の専門領域に特化しているスペシャリストは新たな職場でも結果を出しやすいため、活性化している転職市場での人気も高まっています。
ただ、「一芸に秀でた」スペシャリストを育てるには、それ相応の時間がかかります。また、昨今の義務教育では順位をつけない、他人と比較しないという風潮もあり、自分は何が得意で何が苦手なのか明確にならないまま学生時代を過ごしてしまう人も多いのではないでしょうか。大学教育のあり方など様々な議論はなされているものの、日本におけるスペシャリストの育成は、まだまだ企業による入社後の社員教育やOJTなど業務を通じて実施されるのが主流となっています。
当社の場合も、ITとは直接かかわりのない学科を専攻した文系出身の新卒社員が大勢います。当社のような将来性を期待した新卒採用を行なっている企業でスペシャリストを育成する場合、入社後の新入社員研修や最初の職場で、なるべく早く一芸となる専門領域を見つけられるようサポートすることが重要になります。
人間は好きなことや得意なことは継続できるし成果が得やすいものです。まずは入社後の研修やOJTを通して自分が「やってみたい」「これは得意かも」と思えることを見つけ、それを所属長に伝えることで実際にチャレンジする機会を得る。そんな職場環境が広がっていけば、入社後の早いタイミングで「これだけは負けない」という"何か"を社員は見つけることができるのではと考えています。
あとは本人が第一人者を目指してがむしゃらに頑張る。何事も他人より抜きん出るためには大変な努力が必要です。その努力の過程で自分に「自信」を持つことができた時、はじめて周囲からスペシャリストとして認められるのではないでしょうか。
重要なのは、その人の「価値」です。「自信」とは自分の「価値」を確信することです。一人ひとりの社員が自社の仕事の中で、自分の「価値」を確信できるところまで会社として可能な限りサポートしていくことが、「一芸に秀でた」スペシャリストの育成における企業の責務だと考えます。
社員全員が何か一つ「これだけは負けない」という特定領域に対する深い知識や技術を持ち、「自信」を持って行動できるようになれば、企業としての競争力も魅力度も必ず向上するはずです。
2025年9月
ライター

代表取締役社長
瀬川 文宏
2002年 SO本部システム技術部長、2008年 取締役、2015年 専務執行役員、2017年3月より専務取締役、2021年3月代表取締役社長に就任。現在に至る。
持ち前のガッツでチームを引っ張る元ラガーマン。
最新の記事
年別
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読