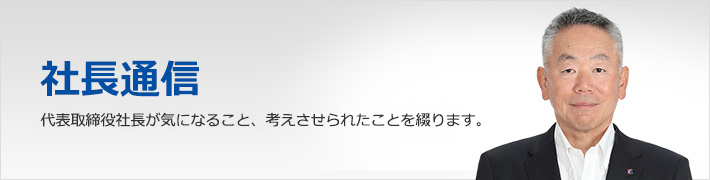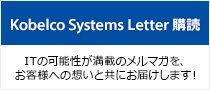2025年10月01日
大谷選手のために作られた「大谷ルール」の持つ意味
~例外的な能力に対応する人事制度~
 前回のコラム*1で触れたように、プロ野球のDH(指名打者)制は1972年に投高打低が激しく観客動員にも苦しんでいたメジャーリーグ(以下、MLB)のアメリカン・リーグが採用し、日本でもこれを参考にして1975年からパシフィック・リーグが導入しました。そして、これまで「野球は9人でやるもの」という伝統を守るべきだと不採用を続けてきたセントラル・リーグも、2027年からの導入に踏み切ることになりました。
前回のコラム*1で触れたように、プロ野球のDH(指名打者)制は1972年に投高打低が激しく観客動員にも苦しんでいたメジャーリーグ(以下、MLB)のアメリカン・リーグが採用し、日本でもこれを参考にして1975年からパシフィック・リーグが導入しました。そして、これまで「野球は9人でやるもの」という伝統を守るべきだと不採用を続けてきたセントラル・リーグも、2027年からの導入に踏み切ることになりました。
もともとDH制は「一芸に秀でた選手」を試合で起用し、より質の高いプレーを提供することでファンの増加を狙ったものでした。しかし、この「一芸に秀でた選手」のためのルールが、「二芸に秀でた選手」の登場によって見直されることになります。そう、大谷翔平選手の登場です。
投手としても打者としても超一流であるため、「投手で降板した後もバッティングは見たい」とファンが思うのは当然ですが、2021年まではそのような起用はルール上認められていませんでした。そのため同年のMLBオールスターゲームで投打の両方でのプレーを見られるように大谷選手を「1番・DH兼先発投手」として起用。この起用を受けて、2022年からは、先発投手がDHを兼務し、降板後も打席に立ち続けることを可能にする、いわゆる「大谷ルール」が正式に導入され、日本でも翌年から適用されています。同年に世界最大規模のデジタル辞書サイト「dictionary.com」に新語としてこの「Ohtani Rule」が追加されたように、まさに大谷選手のために作られたルールなのです。
プロスポーツは興行であるため、多くの観客を集めたり、高い視聴率を獲得したりすることで収益を上げ、ビジネスとして成り立っています。たとえば、世界中で人気のあるサッカーは「祭り」や「遊び」から発展したとされる一方で、植民地時代から西部開拓時代にかけて娯楽が少なかったアメリカでは、スポーツは早くから「エンターテインメント」の一つとして発展してきたと言われています。
そんな背景から、アメリカのプロスポーツには「お客様」であるファンを魅了し続けるために、ファンが求めるものや面白いと感じる要素を敏感に察知し、必要に応じてルールを躊躇なく変更していく姿勢が求められます。前述の「大谷ルール」はその象徴的なものと言えるでしょう。
他にも、野球は他の競技と比べて試合時間が長く、プレーが止まっている時間も多いため、MLBではファン離れを防ぐ目的で、試合時間の短縮に向けた積極的なルール改正が行われています。たとえば、投手が捕手からボールを受け取ってから投球するまでの時間を制限する「ピッチクロック」や、投手による牽制球はプレートを外す動作も含めて2回までとし、3回目はアウトを取れなければボークとするルールなどが追加されました。
一方で、一度採用されたダブルヘッダーの7回制は廃止され、9回制に戻されました。まずやってみて不評ならば元に戻す。つまらないものは排除する。この辺の潔さもアメリカの「とにかく試してみる」文化が影響しているのかもしれません。
これらのルール変更について、MLBの関係者は口々に「これはファンのためのものだ」「リスクはあるが、リスクなしに変化することはできない」「長期的な視点で見れば、必ず有益なものになる」と断言しています。
日本企業におけるルール変更はどうでしょうか。社内制度の改定については保守的な傾向が強く、組織の伝統や既存のルールが重視されるため、短期間で大きな制度変更が行われることはほとんどありません。新しい制度を導入するよりも、既存制度の枠内で工夫を凝らすことが重んじられる文化が根付いています。
とくに人事制度においては、「メンバーシップ型」雇用を基盤とし、「全員にとってわかりやすい公平性」が重要視されています。企業の競争力の鍵はトップタレントの確保にあると言われている一方で、実際には、特定の優秀な人材に特別待遇を与えることで組織全体の公平性が損なわれることを懸念し、大谷選手のような卓越した能力を持つ社員であっても、「例外的な」処遇が与えられることは稀です。
しかし、今後AIがコモディティ化する時代においては、AIを使いこなしつつ、顧客を惹きつける新たな価値を創造できる人材が、企業の差別化要因となるでしょう。このような人材の多くは卓越した能力を持つ多様なスペシャリストであり、彼らがその専門性を最大限に発揮できる環境を整備することが企業にとって不可欠となっています。
従来の公平性を維持しつつ、例外的な才能にも柔軟に対応できる人事制度への転換が急務です。具体的には、社員が安心して働ける環境を確保するために「メンバーシップ型」雇用をベースにしつつ、卓越した人材に対しては「ジョブ型」雇用を適用するという、「ハイブリッド型」の雇用制度も有効な解決策の一つとなるのではないかと考えています。
ご参考
*1:野球界で加速するDH(指名打者)制の採用
https://www.kobelcosys.co.jp/column/president/20250901/
2025年10月
ライター

代表取締役社長
瀬川 文宏
2002年 SO本部システム技術部長、2008年 取締役、2015年 専務執行役員、2017年3月より専務取締役、2021年3月代表取締役社長に就任。現在に至る。
持ち前のガッツでチームを引っ張る元ラガーマン。
最新の記事
年別
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読